第3回 2025年3月_会津紀行 その2
2025.03.19

前回に引き続き、かめっち先生の会津の様子です。ようやく食味の講演会の話、そしてその後の飲み会の話です。(とても長いので、何回かに分けてお送りしています。今回はその第2回です。)

講演会
食味にかかわる講演会自体は割と知っている内容も多かったので、新鮮味には欠ける印象だったが、講師の先生が「味覚までは科学で説明できるが、『おいしいとは何か』という問いへの答えを単純に物質だけに起因させることは不可能だ。例えるならば『幸せとは金だ』などと断定できないのと同じ。」と最後に言い切ったところは新鮮だった。この結論だけでも、講演会に来た意味があったなと感じた。
そのあとの参加者みんなからの自由な質問の数々(お米のコンクールでは一番おいしいものをえらんでいるらしいが、「おいしい」がないのに何で決めているのだ?昔習った味覚マップというのはうそだったのか?とんかつの脂身のような油味は5味には含まれないのか?アルコールを飲んだ時の感じは味覚とは違うのか?「おいしい」はわからないのに「おいしい」はあるのか?)もなかなか面白く、「おいしい」から哲学が発想されるとは思わなかったので、結局全く退屈しなかった。
その後、グループディスカッションに移った。

コロナに罹患された調理人の話だが、「味覚障害の結果、コーヒーの味が分からなくなった。調理をやっていたからこそ自分の味覚が戻ってきているのかがわからない。」といった職人ならではの不安や、「調理人として重要なのは『この調理法をこの食材に使うんだ』という自分自身の思い込みではなく、食材のコンディションを見極めたうえで、『今日はこの調理法にすると食材が最も生きるな』という価値観で調理をすることだと思う。」といった貴重な意見を交換することができた。
生食の果物ですら、調理人によってさらなる付加価値を付与してもらう必要もあるし、そもそも自分もレストランなどでとてもおいしいものに触れてきた経験が多くあるので、今後の生鮮品普及ライフワークにおいて調理者との協働は欠かせないなと再認識できた。

講演会後の飲み会(その1)Tさん~プログラマーの話と援農支援の話~
講演会後の飲み会で、今回の会に声をかけてくれたTさんと、お仕事に対する姿勢、工学系の教員やプログラマー上がりのエンジニアで構成されたメンバーによる街づくり関連プロジェクトに関しての現場をないがしろにしたシステム開発スキームへの危機感などを共有しあい、非常に盛り上がった。

Tさんは、元々地質学を専攻しており、そういった観点からフィールドワークは織り込み済みのものとして事業に向き合っていくという考え方を持っており、その点で深く意気投合して今回の会に至った経緯がある。そしてそのTさんが最も懸念されていたのが、「プログラマーたちに現場の事情を見聞きし調整することの重要性を説いても、全く理解されない。」という点だった。これは自分も農業ベンチャーに在籍した際に一番感じたことだったため、強く反応してしまった。
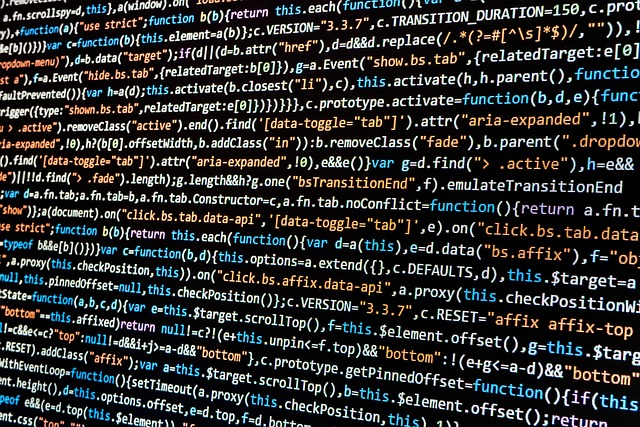
プログラマーは、プログラムとしての運用性やコードの無駄のなさ、動作性などといった尺度によって評価されているため、現場で起こり得る不測の事態や日々ヒューマンエラーの嵐である状況をよくわかっていないからだと思われる。ただ、これらは「プログラマーの責任」というよりも、そもそもプロジェクト化する前に小さく始めるようなパイロット現場を用意しないという「プロジェクトメンバー全員の責任」であるとも個人的には感じている。
Tさん自身現在は、愛媛にて地域商社のような事業を開始し、その中で農業ハウスを使った援農支援ができないかとお話ししていたので、何かしら枠組み作りで力になれればいいなと感じた。施設ももちろん重要なのだが、面倒を見てくれる地縁づくりも同時に進めることが、新規就農者の安心に直結する。個人的には、①生活をする上で地域と新規就農者をサポートする人員配置、②営農活動を進めるうえで教育者たる人員を地域内で探索すること、という2点を迅速に進めていく必要があるように感じた。これらを実現するために必要な補助金があれば取りに行ってもいいし、そもそも就農支援に需要があるのかといった部分も現地に言って調査しなくてはいけないだろうと感じた。そのような現地調査はお役に立てるかもしれない。

講演会後の飲み会(その2)Nさん~「身体性」と「建前」と「登呂遺跡」~
旅館での懇親会にて、今回の会のもう一人の発起人であるNさんというお米問屋さんとお話しした。

講演会の仕切りの時から、「『身体性をもった』という概念を最も大切にしたい」と言われていて、お話をしてみたいという気持ちがあったものの、かなり極端な物言い(科学がどんどん細かい領域に入っていくことに意味がない、に近いこと)をしていたため、ちょっと2人で話すのはおっかないなと思い当初敬遠していた。が、少ししてNさんがこちらに来られたので、心の準備のないまま少し恐怖を持ちつつ会話を始めた。

まず初めに、「身体性」の部分は農業にとっても決して消えることのない概念なので、僕もNさんの考え方がものすごく腑に落ちるといった感じで、正直媚を売りに行った。彼は「いいんだよ、科学は好きに発展して、どんどん未知のデータをとって、新たな方向への進化を遂げてくれればね。でもさ、結局現場にそれを実装するとか言い出すとそれは話が違うでしょって思うのね。俺もどっちかって言ったら新しい研究成果とか面白いデータとか大好きな人間だからさ、研究者がどんどん自分の方向を突き詰めたい気持ちはすごい分かるのよ。でもだからこそ俺はそっちに行っちゃダメだろと。俺は現場で商売を行う人間として絶対(現場)にいないとダメなんだよ。」と言っていた。

Nさんの極端な物言いは、自分自身を律するために発していたのだなということが何となくだが読み取れた。少しでも油断すると、自分自身も研究の方へ関心が流れていってしまうかもしれないことに対して、強い語気を見せていたのだなと。彼はおそらく「現場」の生産者が日々向き合っている「現実」に対して大きな敬意を払いたいと思っており、それが報われるように商いすることに価値を見出しているのだととらえると、いろいろな行動に合点がいくなと感じた。
なので、食味コンクールについても、「あいまいに金賞などと決めて、味の方向性(硬さと粘りのバランスなど)の中で競わせることもしていないため、(コンクールが)むしろ農家を苦しめている現状がある。もし競わせるなら、『おいしさ』などという漠然とした定義もできないものをゴールとしてはいけない。」と苦言を呈する一方で、「農家も農家でそんなものを気にしすぎるなと感じる」と、農家自身がもっと自分の農法に自信を持ってほしいとの意見も持っていた。

何となくだが、建前的なもの(マーケティング、ブランディング、アプリケーション、コンテスト)に大きな違和感を持っているのではないか。もっと目の前にある食材それぞれに触れて、それに対して「自分」はどう感じたかを大事にしてほしい、国民一人一人が自分の持つ「おいしい」の感覚を他者に説明できる国民になってほしいという思いを感じた。建前の話の中で「自分の属する町内会で、LINEを使った方がいいか、という相談をされたときに、誰もスマホを持っていないのに隣町がLINEを使い始めたことを気にした結果、導入を検討している方に対しても、食味と似たような居心地の悪さ(建前的な何か)を感じた。」と言われていて、「『何か起きたら大声出せばみんな聞こえるでしょ。』といって説得した。」といった話は、面白いのだが素直に笑えない話だなと感じた。
ここまでの会話で、Nさんの「科学的なことにものすごく関心がある質であること」、「現場の人間に報いる商売をしたいと思っていること」、「形式的なだけで、本質を見ないような建前が嫌いなこと」という性質が分かったのだが、一方で、お米問屋として商売を成立させるためには「ブランド」や「食味」といった建前のど真ん中を使わないでどうするのだろうと疑問に感じた。また、本日の講演会でも「おいしさに一つに定まる答えはない」という結論をNさんはとても満足していた。

しかし、実際食育などの現場にも携わる身として、子供に対してどのようにお米の価値を伝えていくのかについて興味がわいた。そこで、単刀直入に「子供に対する消費喚起、あるいは食育としてどのようなことを行っているのか。」を尋ねたところ、登呂遺跡で行った食育事業について教えてくれた。
まずは、小学生を相手にしたコメの話をするとき、30キロ袋に入ったお米を子供に持たせるらしい。たいてい重くて持ち上がらないとなり、3人でやっと持ち上がるような具合なのだが、これは君たち一人ひとりが消費する1年分のお米の量(重み)だ、というように教えると実感を身体性とともに理解することができる。また「じゃあ一杯の茶碗に入る米粒は、何本の穂に相当すると思う?」という質問を田んぼの中で子供に問いかけ、大体3穂くらいで1杯に相当するとすれば、1平米あたりの穂の数でお茶碗何杯分のお米が作れるかを計算でき、さらにはこの田んぼで作れるお米はみんなの生活の何日分のお米だろう?といった自分の身体の延長線上に、田んぼを感じることができるのだと語っていた。

子どもへの説明はここでは終わらない。「この田んぼだけだとみんなの生活のたった4日分だけしか作れないなら、1年分のものを生産するならあと90枚この田んぼが必要だとなる。それはみんなでは無理だよね。ならば機械が必要だね。」といったようにあたかも歴史を追うような形で現在の水田へと姿を変えていった経緯を説明していくという、非常にシンプルかつ鮮やかなものだった。ここには食味の話は一切出てこないが、すべて生産現場で一番知ってほしい労働のことが描かれており、一気にNさんに引き寄せられた気がした。この人は自分の筋を絶対に通してきたんだなという気合がものすごく伝わって、めちゃくちゃNさんのことが好きになった。
その話の流れで、弥生時代にお米が入りたての時の稲作風景のお話もしてくださった。

昔は均平をとるような今の水田風景では決してなく、むしろお椀状になっており、真ん中の部分に水がたまるようにして、そこに稲を植えていたのだと教えてくれた。ここで、その元水田だったとされる遺跡に、なんだか不規則な人間の足跡があり、この足跡は何だと思う?と質問してきた(この質問癖は静岡農家集団特有のものなのだろうか)。僕は、穂が実った順番に収穫したから不規則なのではないか、と答えたが、Nさんはとてもうれしそうに「君はまだ現代の水田体系の刷り込みから抜け出せていないね。」と悪魔のように笑っていた。(質問から嘲笑までがセットの伝統芸能なのだろうか)
正解は、田んぼの中に入ったうなぎや魚を捕まえるために人間が追いかけた足跡だろう、と教えてくれた。確かにそれはつじつまが合うし、食生活の中で絶対的に必要になるたんぱく源摂取を行う必然性もあるなと、面白い考察に少し悔しさを覚えた。ある種、Nさん自身、登呂遺跡でのこうした事業に取り組んでいく中で、現代においてあまりに多くはびこる建前の多さに気づき、うんざりしたのではないかなとも思った。
余談だが、登呂遺跡の事業が使っていた「タイムマシーン(新幹線)に乗って、東京から1時間で2000年前にタイムスリップ!」というスローガンはとても面白いなと感心した。

そこから話はそもそも狩猟採集民族がどのような生活をしているのか、といったところに飛んでいった。
アマゾンの先住民たち(今も現存)は、1週間の食糧を確保するためにどれだけの時間を費やしているか?という質問(伝統芸能!以下略)をされた。
自分は過去に読んだ文献の知識から、「ほぼずっと食料を探しているはずだから、1日10時間程度」と答えたが、答えは「その日の午前中には作業が終わる」というものだった。確かに、自分が読んだ文献はクロマニョン人の話だったので、そこまで資源が豊富な場所ではない。アマゾンならばそれくらい資源が豊富なのかもしれないなとまたしても悔しい思いをした。

さらに質問を繰り返され、では先住民は余った時間に何をしているか?という問いに対しては、「武器の調整など」と答えたところ、「基本的には性交渉、子供との遊び、猥談のどれか。」との解答を突き付けられ、これはなるほど、となった。Nさんの「俺たちだってこれだけでよくない、って思う時あるじゃん。」というセリフが地味にツボに入ってしまった。
話は社会教育に移り、登呂遺跡で3年間ぶっ通しの「当時の生活を振り返る」という講座をしていた時のお話をしてくれた。それによると、「この人大丈夫か?」といった雰囲気のハイソなマダム(高級ベンツ所持)もこの半サバイブ的な講座に参加してきており、しかも3年間通い通してくれたらしい。

内容としては、最初に当時の道具を使いこなしながら、なぜこのような形になったのか(当時の技術の限界や、鉄や青銅といった原材料について)や、当時の稲作風景はどんなだったか(前述のすり鉢型の田んぼについてなど)に触れつつ、少しずつ登呂遺跡に暮らしているのだという刷り込みを参加者に行っていき、最終講座では皆で当時の道具を使いながら実際に煮炊きを行い、食事を作ろうという試みを行ったらしい。
その時に、マダムが空を飛んでいる鳥を見て、「あれ食べてもいいよね」と発言したとき、Nさんは「おっしゃ!大成功だ!!」と心でガッツポーズを決めたという。

このエピソードを聞いた直後はただただ大爆笑していたが、これこそが社会教育の本質だと感じた。完全に没入してその状況に身を置かせることができるのは、講座を取り仕切っていたメンバーの努力に他ならないし、このようにして得た一体感は、言語化する際にもものすごい力を発揮する。一度この講座に参加した人たちからも感想などをヒアリングしたいなと思った。
さらに話は流れて、食や美に関して、形式的においしいとされているものから逃れて、自分が「良い」と思うものをどう他者と共有しあうか、についての話題となった。
僕が、現在美学の本を読んでいて、多様性理解と美的解釈の共有は同じ原理で動いているような感覚があるという話をしたところ、文化的な話という観点で、昔あった給食センターでの出来事をお話ししてくれた。
少し前に、何人かの児童から「給食で配膳されるお米から異臭がする」というクレームが来た。調査をするために調理現場を訪れたが、想像以上にきちんと行き届いた管理を行っていて、とても誠実な現場だったのだそう。

ただ、実際に配膳されたお米は、異臭ではないものの本来お米からする香りではなく、どこかで嗅いだことのある香りだったらしい。何度か嗅いでみると、どうやらイーストのにおいだということに気づき、その調理現場が同時にパン焼きも行っている現場っだということに気が付いた。
結局お米の調理過程に大きな変更はなく、炊飯後にお米の移し替えを行う部屋を変えるだけで対策できたのだが、今度はその小学校の卒業生から、「このイーストの匂いがうちの小学校のお米の香りなんですけどね。」といわれたらしい。
普通、家のお米を食べていれば、このお米からする香りが普通ではないことくらいわかりそうな気もするが、このイースト米も一つの文化だったのかもと考えると、意外と複雑な問題かもしれないと少し悩んだ、といったことを教えてくれた。これに関しては、イースト米が食味にどれだけの影響を与えていたかわからないので何とも言えないが、決して毒ではないことは明らかなので、なかなか一つの正解を作るのは難しいかもなぁと思った。

最後に、また話は先端科学技術に移り、Nさんはここでも「俺はむしろ本当にこういった分野が大好きなんだ。ただ、これは専門家に聞けばいいだけなんだよ。けど専門家がちっともわかりやすく伝えてくれない。専門家を名乗るのであれば、伝えるまでが役割だと思う。」とおっしゃっていた。なので、Nさん自身も、例えば甘みを伝えるときは「サツマイモのように甘い」や「栗のように甘い」といったニュアンスをきっちり表現することを意識している。なにか相手と話していてつじつまが合わないと感じるときも、相手の使っている用語を自分が使っている用語と重ねてみて、じつは同じ言葉で全く違う事象を想定しているといったことがかなり多い事実にも気が付いたと話していた。ここにいち早く気付き、修正できる能力は、営業だけにとどまらず、何かを広い対象に説明していく際に問われ続ける能力だろうなと思った。

かめっち先生、講演会後の飲み会がまだまだ続きます・・・

 一覧へ戻る
一覧へ戻る