第1回 2025年2月_岡山紀行
2025.03.17

Fさんと初対面
お役人カイギで意気投合したFさんと初対面。生成AIや農業の融合などといった今自分のやりたいことや、以前Fさんと、共通の友人のAさんしていた「感覚派か理論派か?」といった話で盛り上がる。
この時は、Fさんが自分と同じ香車タイプだと思い、ものすごく楽しくお話ができたが、この後でFさんがもっともっとすごい方だということを徐々に気づかされていく旅となっていく。その後少ししてOさんも合流し、車の中でOさんの紹介(ちょっと最近モチベーションの維持に苦しんでいる)や、そのほかの雑談をしながらK農産に向かう。

K農産
15分ほど走って、K農産さんに到着。岡山県最大の180haに及ぶ水田を管理しているという前情報からは想像できないほど穏やかな会長さんが迎えてくれた。
岡山県南区にある藤田地区は、日本3大干拓地(ほかに有明、八郎潟)に数えられる場所であり、田の1枚当たりの面積が広く形も長方形で機械が入りやすい農地基盤整備がしっかりしているという特徴がある。そのため、耕作放棄地はあまりなく、非常に農地としての生産力が高い土地となっているらしい。
Kさんは、100~120haほどを酒米(山田錦・雄町)生産に利用し、ほかはヒノヒカリなどのうるち米や丹波黒などの大豆、裏作で二条大麦やはだか麦といったものを栽培している。コシヒカリのような早生品種が登熟を迎える9月は、岡山県はまだまだ気温が十分に下がらず、品質の良いものは取れないということで作付けはないようだ。
現状の課題としては、単品種で10haもの面積を抱えるため、一気に収穫時期を迎え、最も品質がベストな時期に収穫を終えるためには超短期集中で臨む必要に迫られてしまうという点があげられる。さらにその結果、大量の農業機械を所有せねばならない課題もあるとのことだった。

Kさんとお話ししていて一番感じたのは、広い面積を管理していながらも、非常に研究熱心で、経営者よりむしろ研究者・職人寄りの方だということだ。その気質ゆえに、夏場の気温上昇に関する対策を議論した際、「水温管理の問題だと思うのだが、水をためすぎると夜に水温が下がりきらず、稲はお風呂でのぼせてしまった状態になるという説があるため、徐々に水を抜いたうえで新しい水に入れ替えるということを試したり、一方で深水にする方が水温自体は上がりきらないのでやはり深水にして管理する区を設けたりなど試行錯誤している。」といったリアルなコメントをいただけたのがとてもありがたかった。さらに「根圏が30cmよりも下まで行くと、地温が15度で年中一定になるので、サブソイラを利用して土壌を柔軟にし、根張りを下に深くするような努力もしてみたいと考えている」という、より深い研究的な思考もなさっていて、やはり篤農家さんだなと感嘆した。
その一方で、土地集約性の高い農業(二毛作による土壌の酷使)を実践していることから、反収が7俵と、その土地の平均から比較すると物足りない結果に終わっていることを憂いている。正直、180haを回しながらそれだけの収量を実現しているのは本当にすごいとしか思えないが、ここが会長の会長たるゆえんで、意地でも収量を向上させたいという気持ちが伝わってきた。
そのような中で、FさんがJ-クレジットをうまく利用して、循環型農業の実践によるブランドと補助金の両方を得たうえで、自社もみ殻を原料とするバイオ炭施用による知力向上を目指すという画期的なプランを動かし始めている段階だという。このような、Fさんの「農家のかかりつけ医」としての分析・提案能力は農家にとって欠かせない知見であり、それを農家さんの特性・能力・傾向に合わせて提案できるのは、行政で培ってこられた「国・政府のやり方に対する深い理解」、農業現場に足を踏み入れ続けたことで蓄積された「農家情報のデータベース」、そしてFさんご自身が持っている「人間や組織に対する分析能力と、それにより導き出された答えを迷わず即決できる決断力」に他ならないなと感嘆した。
循環型肥料としては、丹波篠山にてK農産から出たもみ殻、黄桜酒造から出た醸造後の搾りかす、丹波篠山の落ち葉などによって製造されたものを利用し、バイオ炭は自社付近に作った精製工場にて自作しているとのことだった。次回の訪問ではこのあたりも是非視察させていただきたいと思った。

会長との話は流通に移り、今のところは米1俵あたり2万円を超えるようになってきたので、以前よりは経営はやりやすくなってきたと話しておられた。また、今年は普段とは異なる業種からコメを売ってほしいという問い合わせがかなり多く来たということも教えていただいた。海外への輸出に関する話になると、中国人をはじめとする大陸の人間はとても商売上手で、「昔、中華料理の経営者と交渉したことがあったが、こちらに在庫がないことを説明したところ、キロ単価で100円上乗せして買わせてほしい、といった提案をしてくるように、生産者側が十分に満足し、自分も付加価値付与によって利ザヤが発生する価格の見極めが非常にしっかりしている」という具体例をもとに、とても分かりやすく説明してくれた。そのほかにも、卸業者(特に大陸系)は大量に仕入れを行った後、小売りに小さなロットで分配する際にもなかなかの中間マージンを取れる仕組みがある、といった生々しい情報も教えてくれた。現在、中国では味覚の贅沢化がかなりの勢いで進んでおり、日本のお米はとても人気があるのだそう。現在輸入米にかかる関税はキロ350円で、元の価格が350円の合計700円で輸入米が売れている状況を見て、国産米はもっと値上がりしてほしいともおっしゃっていた。自分が見聞きした情報でも、中国の水事情はかなり深刻で、中国国内の富裕層は自国産の米のことを全く信用していないらしく、日本の水源がある土地を買収しつつ、日本産米を買い占めるような方向で動き出しているという話があったので、これを機に、日本産ブランドを確立して、正式に海外へと大きなロットを携えた状態で参入していく方が効率的であり、その時にK会長のような方がリーダーシップをとって生産者をまとめてくださるといいのだろうなぁなどと考えてしまった。
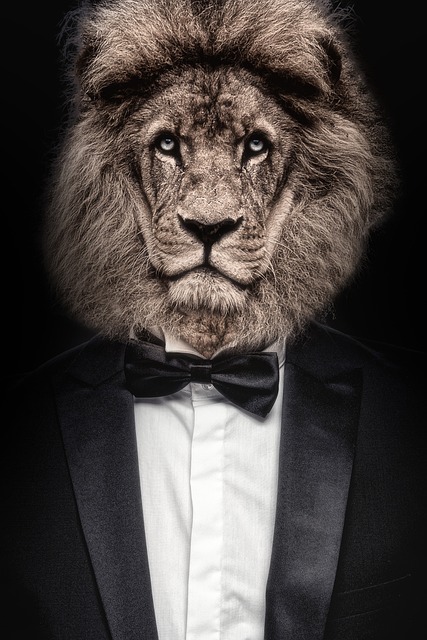
続いて話は経営・社員教育・将来の展望へと移っていった。K会長は女性職員が生き生きと働くことができる職場を目指しており、それが農業を次のステージに推し進めると考えているらしい。このあたりを幅広く考えることができるK会長の視野の広さに驚いた。確かに根っこの部分では技術者なのだが、この方はそれにとどまらないビジョンをもっており、自分たちの経営体だけでなく、地域、ひいては日本国内の農業生産現場をよくしたいという強い気持ちから、みんなが必要なお金を稼ぎつつ、楽しく向上心を持った営農を志せる環境が作りたいのだろうなぁと、その高い志にものすごく共感した。また、それに関連した会長のアイデアはとても興味深く、「女性にトラクターの操縦を覚えさせることで、後ろの苗床運搬などの力仕事を男性職員に任せることができる」という、思いつきそうであまり誰もやっていない方法を教えてくれた。
一方で、社員教育に関しては試行錯誤が続いている現状も共有してくれた。ご自身の息子さんであるところの現社長は、もともと某世界的な自動車メーカーに勤務しており、そこを退職して事業を承継されたようで、社長は「ほかの産業と農業を比較した際に最も見劣りするのは社員の給与なので、まずはそこを改善する」という方向を示したそう。一方で、会長はお金だけでモチベーションを維持できるのかという疑問を抱いているらしく、職場環境の風通しのよさや、技術を磨きたくなるような理由付けを何とかして見つけたい、といった悩みを打ち明けてくれた。

この後での話になるが、Fさんが「継承された社長さんはとてもよくやっている。例えば、獺祭の旭酒造主催の『酒米コンテスト』参加の機会を利用し、社内に3グループ作り、より高品質なお米を生産できたグループには、コンテストへの出品と10万円の賞金を渡すという仕掛けを考え、社員同士の腕を競わせた。その結果準グランプリを獲得して1000万円の賞金を得るとともに社員の技術向上につながった。グランプリであれば3000万円なので、次回はグランプリを目指すという。これは高いモチベーションと技術アップにつながると思う。」と教えてくれた。また、農業法人の社員インタビューでは、他の農業法人に比較して、K農産の社員たちは「非常に雰囲気が良いため働きやすい」といった感想を多く寄せていたらしい。このようにK農産がとてもうまく機能している要因は、社員に技能や給与などのキャリアをまずはシステムという形で付与するという新社長と、会社自体の雰囲気づくりや、経験と知恵によるアドバイスで社員のメンタルをケアする会長とのいいバランスが自然と維持されていることなのかなと思った。現に、現場管理責任者は15年勤務しているそうで、これは農業法人ではかなり異例の長い経歴だと思う。将来的には定年まで働くことも視野に入れられるような農業法人も、国の食糧管理という観点では大事になるという話を山梨県庁のSさんともしていたこともあり、K農産には、経営者としての心や、経営と人情のバランスの見本として、いろいろの農業法人の鏡であり続けてほしいと心から感じた。

お昼ご飯
お昼はぶっかけうどんのチェーン店にて山掛けうどんをいただいた。岡山の讃岐うどんはとてもおいしく、山芋とうどんの組み合わせに大きなパワーをもらえた気がした。ここでは主にFさんと「JAのあるべき姿」や「役所の若手人材をどうモチベートしていくか」などの話で盛り上がった。Fさんのおっしゃっていた「JAはとても大きいロットと農家情報が自然に入ってくるのだから、もっと多様で面白い出口戦略がいかようにも取れるはず。それなのに国の備蓄米の流通を独占したり、全く創造的でないことに終始しているのがもったいなくて仕方がない」というお考えに強く共感した。自分としても、農協を解体するかどうかは差し置いても、今の農協のやり方(特に出口戦略)を刷新しなくては農業が人気な産業にはなりえないという考えを持っている。そのため、生産者の生産物を、様々なアイデアを凝らして消費者に伝えていくための販売戦略グループ(デザイナー、料理人、SNSのハブユーザーなど異分野の人々で柔軟な意見を交換できる場)と、それを実行していく実務系のグループ(交渉、書類作成等の調整ができる人々)の必要性を感じていた。Fさんはこの2つのグループを橋渡しすることができる人材だなと確信した。

H農園
お昼の後、県の栽培普及員を勤めつつ、自園地にて柑橘類の栽培にも従事するスーパー変態公務員の Hさんと、ミカン園・レモン園にてお話しした。
Hさんは、もともとミカンや様々な果樹をお父さんと一緒に栽培していたそうで、特に桃に関しては弱剪定により、窒素の樹体比率を下げながら、摘蕾をより重視した栽培管理方法を実践しており、樹勢のバランスを保ちながら減農薬(つまり労働粗放型)の農法を実施してきたのだそう。現在桃の栽培については、桃の収量が落ちたこともあり伐採して、ミカンももともと40aほど存在した園地を減少させつつ、ほとんどを早生品種にして作業をより負荷の小さい方向にする努力をしている。
ミカン園に関しては、農薬を1回しか打たないというなかなか攻めた減農薬を行っているが、それでも果皮に黒点が多くつくだけで食味には何ら問題がないとのことだった(一般の外観基準だと8割程度がアウトだが、別に概観を気にしないという消費者は結構多いので問題がないとのこと)。ただ、最近は「そうか病」が増えてきており、これは品質に大きな悪影響を及ぼすことから、その時期の前には予防防除をしなくてはならないかもしれないと対策を模索しているらしい(このあたりからOさんのテンションが目に見えて上がってくる)。
このような最低限必要なことだけをこなす低負荷なミカン栽培において、やらねばならない最低限の管理として、①草刈り(特に株本をきれいに刈ってやることで、カミキリムシが卵を産み付けにくくするのと、根域が雑草と競合して生育が阻害されるのを防ぐ)、②開花前のマシン防除とボルドー散布(本来マシンと農薬の混合防除は薬害リスクを高めるとされているが、さほど薬害は気にならないとのこと)、③幼木の周りには柵状のものを敷いておく(イノシシがミミズを食べに株本に来るのを防ぐ)といったことを行っているそうだ。
剪定は枯れ枝の除去以外はほぼしなくても、樹勢は悪くなっていないし、摘果もほぼ無摘果だが、隔年欠果こそあるもののそこまで気にならない程度で済んでいるとのことだった。これはおそらく、株本の草を引いていることで、根圏の生育が正常に保たれており、剪定をしないことから過度の栄養成長が抑えられることで樹勢が落ち着くのかな、と思う。摘果をしなくてもうまくいっているという点はよくわからないが、生理落下するときに結構うまく調整ができているのだろうか。いずれにせよ、根がしっかり出ていればサイトカイニンが優勢になり、花芽は分化するので開花までは問題なくいくということなのだろうか。

倉敷は、元々ミカン栽培の北限にあたる地域で、気温が氷点下5度近くまで達することもたまにあるため、ミカンの木は寒冷紗やパオパオなどで地上部を養生したうえで、さらに株本も藁や新聞紙によって養生する必要もあるという。
実際に木に実っていた黄金柑と、はれひめを食べさせていただいたが、どちらも非常においしくてびっくりした。正直自分は有田という頂点を知っているという謎の天狗になっていたこともあって、Hさんの晴れ姫が持つ素朴で強い甘みに、僕の伸びきった鼻は再生不能なまでに破壊された。このはれひめなら自分が就農したときにぜひ育てたいと思った。黄金柑も、今までに食べたことのない甘みと酸味とフレーバーのバランスで、しかも小さい個体をワンショットで食べるというスタイルは、その爽快さも相まって、文化になるポテンシャルを秘めていると感じた。
その後、姫レモンというライムの園地と、ユーレカとリスボンの園地とを見せていただいたが、ここに至っては完全に無農薬(マシン油とボルドーのみ)で栽培しているらしく、それでいて非常にきれいなレモンやライムが実っていることに驚いた。特に姫レモンは果肉が美しい上に、香りが本当に素晴らしかった。なんというか、ゆずのような強い主張があるわけではないのだが、同じくらい優雅な存在感があり、主役も張れる実力を持っているのに、あえて2番手3番手の役柄でも輝けるという奥ゆかしさと自信を持っている(常盤貴子・佐藤浩市的な立ち位置だろうか)感じがとても魅力的だった。

Hさんは、およそ30年間にわたって農業試験場の研究や、栽培普及で現場を回り続けてきたこともあり、様々な技術とその成り立ちについて大体のメカニズムを把握しているという驚異的な人物だった。その中でも特に「この人は素敵だなぁ」と思ったのは、各栽培管理法に対して、「いいとこ取りをしようというのが間違いのもとで、その栽培管理理論そのものが連続性をもっているので、まずはその理論の通りにやってみて、そこから自分の園地に合わせて微調整をしていく必要がある」と主張されていたことに対してだった。
僕自身も本当に反省したのだが、確かに栽培素人は、一つの技術(例えば剪定)について議論したがる特性を持っているのに対し、本来栽培管理というのは連続しているのだから、その1点だけを取り上げても仕方ないのである(人生もそうで、ミスをしたらそれを補って生き続けていく必要があるので、その1点だけですべての原因とすることはできない)。なので、長い経験の中で生まれてきた、「流れと順序」をもった栽培理論は、流れを追って、さらには常に観察を続けながら適用・改善を繰り返していく営みだということを改めて感じることができた。そういった中でも、可能な限り具体的な方法を指し示そうとしてくれるHさんの姿勢(例えば苦土石灰は夏場に切れることが多いので、梅雨明けあたりに施肥するとよいという情報や、窒素は健全な樹体であれば葉面散布だけで事足りると思うといった情報)に対し、強い尊敬の念を抱いた。
その一方で、話にユーモアと教養を絶妙な塩梅で織り込んでくれるトーク技術や、随所に見せるおちゃめな感じ、さらには栽培を語る際に結局我慢できずに飛び出す濃ゆい「変態さ」こそが、HさんとFさんとを引き寄せた人間的な魅力(臭み)なのだろうと楽しく拝見させていただいた。

倉敷市散策(くだものミュージアム)
倉敷市の観光地域にて散策を行った。
ここには「くだものミュージアム」という、HさんやFさんも協力し、その地域の事業者である犬養毅の子孫が中心となって設立した博物館を訪れた。この博物館は、必要以上に隠れ家感が強くなっており、これは戦略なのかイジメなのかと一瞬考えてしまうほど奥ゆかしい扱いを受けていた(誰も気づかないんじゃないかという不安が正直なところ大きい)。ただ、100年以上の古民家を改修して、果物の歴史をコンパクトにまとめた博物館は非常に充実しており、そこに加えて地元の最も優秀な普及員の方が解説してくださったので、本当に濃密な時間を過ごすことができた。
個人的に印象に残ったのが、「岡山県は一人当たりの栽培面積がとても小さく、まるで盆栽のように樹体に目をかけられる環境が育ったことで、非常に変態的な栽培マニア農家が生息するようになった」という指摘である。あとは、桃の大久保という品種が、本来は劣勢であるところの実と殻が離れやすい性質を有しているという点も、加工用の桃において非常に優秀な利点だろうなと感じた。ここで、桃の殻割れの原因を尋ねたところ、温暖化によって、果実肥大期が早まったことによって、硬殻期(着果後50日前後)前に果実が核を引っ張り破壊してしまうことが原因といっていた。これによって核が栄養を吸収する力の減衰や、核の細胞壊死などが重なり果実も劣化が早くなるとのことだった。また、ぶどうのブルームに対する岡山県民の考え方も非常に先鋭的で、絶対に果実に触れずに作業を行うことを徹底している、とのことだった。
博物館の2階には、くつろぎスペースと果物に関連する図書がおいてあり、普通ならば子供用の絵本などがおいてありそうな雰囲気のスポットに、絵本に交じって変態しか読まない農業系の専門書がこぞっておいてあり、「本当に果物を遍く広めるつもりはあるのだろうか」とおもわず大爆笑してしまった。
そのほかにも、倉敷の魅力が多くありすぎて語りきれないほどだったが、やはり地元の有力者がしっかり地域文化を根付かせるために、金銭をはじめとする努力をしていたのだな、という部分が一番感じられた。というのも、景観を考えるうえで最も重要な歴史的建築物のリノベーションを、町の随所から感じることができたからである。そこに加えてHさん(もはや大先生)の文化解説が加わるのだから、本当に充実した(10万円相当の価値がある)最高のツアーであった。このときに、Oさんが、「(Hさんを完全再現した)HさんGPTをミュージアムに置いておいたらいいね」といっており、やはりOさんの自由な発想は本当にすごいなと改めてその底知れなさを感じた。
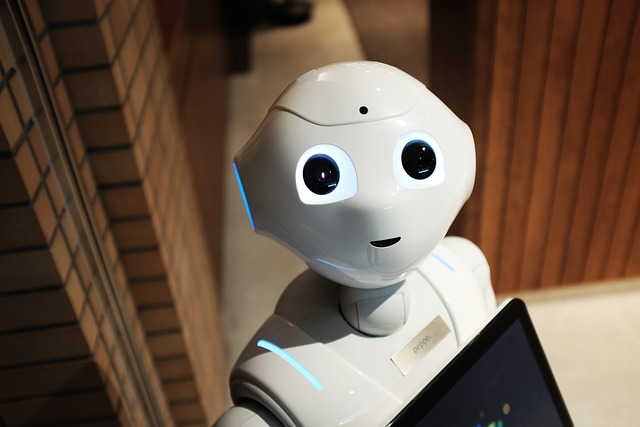
晩御飯
最後に、(晩御飯のお店情報を入れてもいいかも、(ex)姫レモンビールが味わえる岡山でも珍しいお店にて)晩御飯を皆で楽しんだ。姫レモンビールはこれまでに飲んだクラフトビールの中で最もおいしかった。本来ビールはあまり好きではないのだが、これは口当たりがよく、いい意味でサイダー感覚で飲める代物だと感じた。
ここでは、主に岡山県の農家がなぜ変態が多いのかという話(JAのようなトップダウンの集荷・流通組織が卓越しなかったので、生鮮品問屋と直接つながりながら消費者の指向を見極め、生産するという癖がついたから、例えば東京と大阪でシャインマスカットの色を変えるといった事例があるなど)、Fさんの能力がいかに特殊で変態的でかけがえのないものか(生産者サイドと行政サイドの思惑を、事務手続きの方法とセットで見通せるというある種のテレパス的な能力者)、人間をどう分類していくかについて(口だけ評論家タイプ、経営興味なし変態オタクタイプなど)Oさんが有田でどういう農業を行っていくべきか(どのような仮説を立てて栽培管理を実験していくか)、僕のコンサルに対する悪口といった様々な話に花を咲かせつつ、気づいたらかなりの時間が経過していた。

最後の感想であるが、とにかくまた来たい!!!これに尽きる!
本当に最高に楽しかったです!次は(イチゴとブドウの)Tさんやブドウの匠で鷹匠のTさんにもお会いできればありがたいです!!長野、愛知、和歌山に来る際は、ぜひご連絡くださいね!
本当にありがとうございました!!!!!


 一覧へ戻る
一覧へ戻る